Story 03海に投げ入れられた木
愛知県
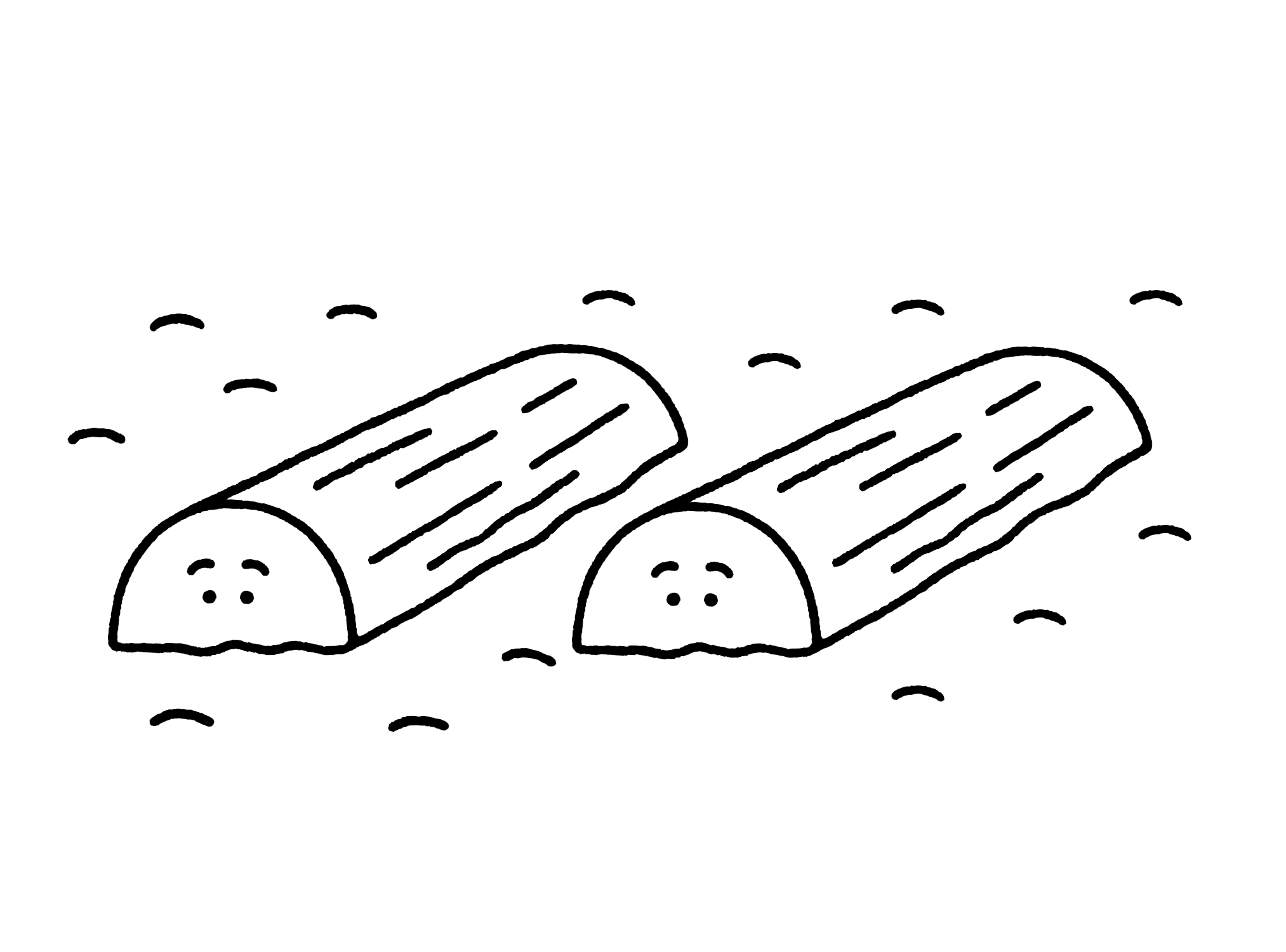
愛知県弥富市にある製材所〈ヤトミ製材〉は、日本でも数少ない木材の水中乾燥をおこなっている場所です。酸素と日光を遮断することで干割れや日焼けを防ぎ、細胞内に海水が満ちることで、反りやネジレを低減させるなど、様々な効果が期待でき、実は1300年以上の歴史を持ち、伊勢神宮の御用材にも用いられている技法です。この水中乾燥では、木材を完全に浸水させる必要があり、その“重し”としてだけ使われる木も多くあります。重しの木の多くは流通から外れてしまったもので、ゴミとして処分されることも多いのだそう。しかしながら、材にはならずとも役目のある「重し」に混ざって、使い道や買い取り手がない木もあることがわかりました。今回は取得したのは、そういったただ海に投げ入れてしまっているだけの木。これらの木をどう活用していくかを探る必要性を感じさせます。



Tree Thrown into the Sea
Yatomi Sawmill, located in Yatomi City, Aichi Prefecture, is one of the few places in Japan that practices underwater drying of timber. By blocking out oxygen and sunlight, this method prevents cracking and sun damage, while the saturation of the wood’s cells with water helps reduce warping and twisting. It’s a technique with over 1,300 years of history and has even been used for lumber destined for Ise Jingu, one of Japan’s most sacred shrines.Underwater drying requires the timber to be fully submerged, and many pieces of wood are used solely as weights to keep the main lumber underwater. These “weight woods” are often pieces that have fallen out of the distribution cycle, with many ending up as waste. However, it turns out that among these functional but overlooked weights, there are also logs that have no clear use or buyer—simply thrown into the sea with no purpose beyond submersion.This time, we’ve acquired some of those very logs—wood that’s been cast into the sea with no intended future. Their existence highlights the need to explore new ways of utilizing such overlooked materials.





